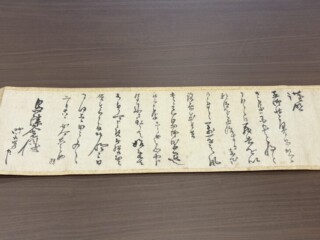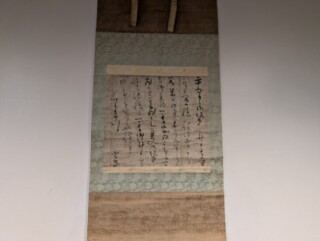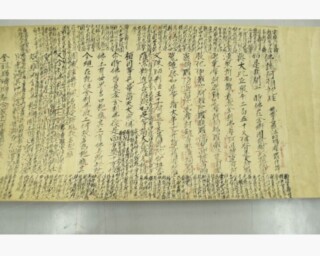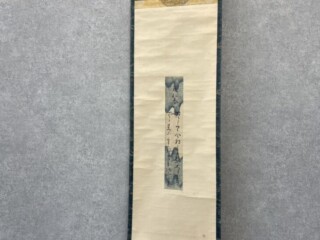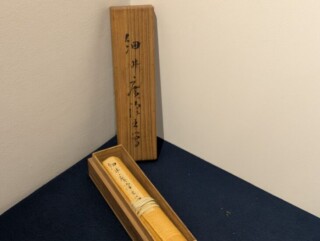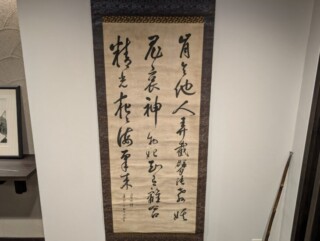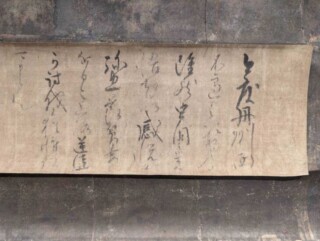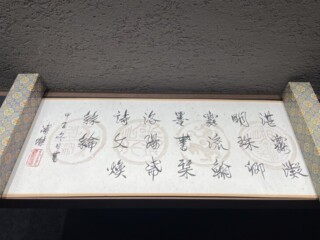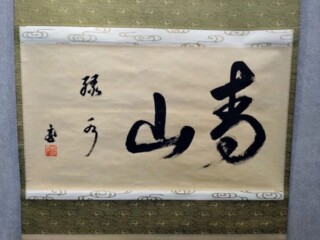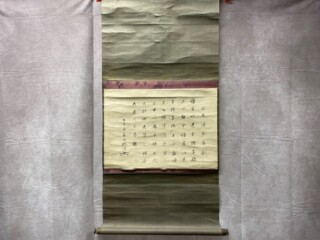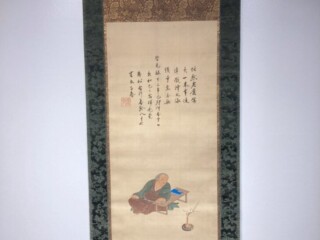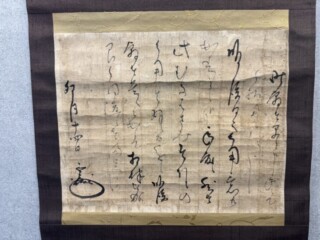徳川家康は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、江戸幕府を開いた初代征夷大将軍です。三河国(現在の愛知県)岡崎城主・松平広忠の嫡男として生まれました。幼少期には織田家、続いて今川義元のもとで人質となり、不安定な日々を過ごしました。
1560年の桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れると、家康は三河に戻って独立し、ほどなく信長と清洲同盟を締結します。その後、三河国の平定を進め、同盟関係の中で戦国大名としての地位を固めていきました。
1572年の三方ヶ原の戦いでは、武田信玄率いる大軍に敗北します。この敗戦は家康にとって生涯忘れられない教訓となり、後に「三大危機」の一つとして語られました。また、三河一向一揆の鎮圧や、伊賀越えなど数々の試練を経験しています。
その後、豊臣秀吉と和睦し、秀吉の天下統一に協力。1590年の小田原征伐後には関東の広大な領地を与えられ、江戸城を本拠地としました。
1600年には関ヶ原の戦いで石田三成率いる西軍を破り、実質的に日本全土を支配する地位を確立。1603年には征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開きました。
家康は軍事的手腕だけでなく政治・外交においても優れ、長期的な安定を目指した統治体制を築きました。その基盤は、慎重さと忍耐を重んじる姿勢に支えられており、江戸幕府が約260年続く礎となりました。
将軍職は早くに嫡男・秀忠に譲ったものの、大御所として実権を保持し続け、1614年・1615年の大坂の陣によって豊臣家を滅ぼし、体制を固めました。
1616年に没した後、まず駿府に埋葬され、翌年には日光山に改葬されました。家康は「東照大権現」として神格化され、現在も日光東照宮に祀られています。