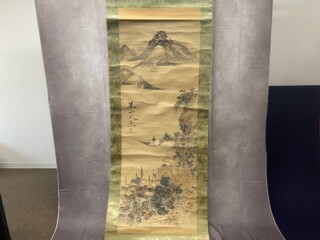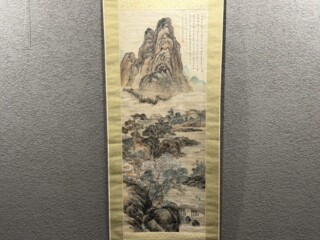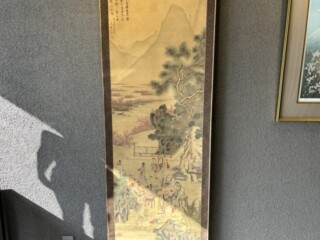山本 梅逸は、花鳥図を得意とした文人画家で「尾張南画の巨匠」と称されています。
1783年、梅逸は名古屋に生まれました。
幼い頃から絵が好きだった彼は、12歳で見事な襖絵を描きあげ周囲を驚かせたという逸話があります。
父親を早くに亡くしましたが、教育熱心だった母親から和歌を教わりました。
はじめは狩野派の山本蘭亭に絵を学びました。
蘭亭は彼の絵の才能を見抜き、次に四条派の張月樵の下で学ばせました。
その後、中国絵画コレクターだった富豪「神谷天遊」のもとで修行をしました。
1802年に天遊が亡くなると、兄弟子の中林竹洞と共に京都へ赴きました。
一度は名古屋に戻りましたが、1832年に再び京都へ出ると人気が高まり、南画家としての地位を確立しました。
彼は巧みな筆使いで、柔らかな花や自然の立体感、生物の動きを表現しました。
花鳥図を得意としていましたが、笛や煎茶道にも造詣が深かったといいます。
彼の作品には『文豹図』『墨梅図』『四季花鳥図』などがあります。