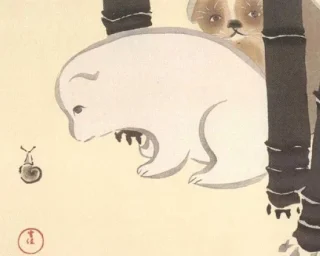尾形光琳は17世紀後半~18世紀にかけて京都や江戸で活躍した琳派の大成者として知られる絵師です。
雅で優雅な伝統を感じさせる大和絵的な描写の中に斬新で大胆な構図や画面展開を取り入れた明瞭でかつ装飾的にもかかわらず革新的な独自の様式を確立し、その独自の様式は当時では最大の画派であった狩野派とは一線を画す「光琳模様」と呼ばれ、日本の絵画や工芸など幅広いジャンルのデザインに大きな影響を与えました。
1658年に京都の呉服商の「雁金屋」の次男として生まれた尾形光琳は裕福な家庭で育ったこともあり、少年時代から能楽、茶道、書道に親しんでおりました。
30歳の時に父が亡くなった後は、長男が後を継ぎ尾形光琳は父が残した遺産を40代までの間に湯水のように使ってしまったとのことです。
長男が後を継いだ会社も破綻してしまっていた為、経済的に困窮したことから画業を本格的に始めたのではないかと言われております。画業を本格的に始めた後は公家や大名など多くの物に経済的に援助してもらいながら、京の裕福な町衆を顧客に数々の傑作を世に送り出しました。
本格的な活動は44歳から没する59歳までの約15年ほどであったと推測されていますが、その間に大画面の屏風のほか、香包、扇面、団扇などの小品も手掛け、手描きの小袖、蒔絵などの作品もあります。
また、尾形乾山の作った陶器に光琳が絵付けをするなど、その制作活動は多岐にわたっております。
三谷吾一は昭和から平成にかけて活躍した漆芸家です。沈金の技法による独特の作風で人気を得ております。
石川県輪島市の塗師の家庭に生まれ、幼いころより様々な職人たちと接します。14歳の時には沈金師である蕨舞洲に師事しました。
沈金とは漆の装飾技法のひとつで、のみで塗面に模様を彫り、彫った後に漆を塗り込んだ後、金や銀の箔や粉などを塗り込んで模様を作る技法です。
蕨舞洲に5年師事し、それから3年間漆芸家・前大峰の下で修業を積んだ後に、22歳で沈金師として独立しました。三谷は今までの輪島塗にはなかったような詩情と構成のあふれる色彩から、絵画のような作品を目指しました。しかし絵画のような表現をするには漆の制約が多い為、技術だけでなくアイデアも必要となっていき、その度に試行錯誤を繰り返していきました。
1965年に日本現代工芸展において、現代工芸大賞と読売新聞社賞を受賞します。その後も様々な色彩を取り入れながら数々の実績を残していきます。独特な中間色で表される表現は、従来の単色で表現される沈金技法とは異なるため「三谷沈金」と呼ばれるようになり、輪島塗を芸術品としての価値を高めていった功績は高く評価されています。
加賀蒔絵を代表する作家の一人が「清瀬一光」さんです。
加賀蒔絵とはその名の通り江戸時代に加賀藩で作られた蒔絵技法の事を言います。
加賀藩の三代目藩主であった前田利常は文武の一環の一つとして京都から「五十嵐道甫」江戸から「清水九兵衛」が招かれ現在の加賀蒔絵の礎が作られました。
「清瀬一光」は当代で二代目となり初代の長男の方が二代目「清瀬一光」を襲名されています。
二代目「清瀬一光」さんは「加賀蒔絵」の伝統を守りながらも様々な新しいことに挑戦されています。
今まで一般的に蒔絵というと木製の漆器に施されることが多かったですが、二代目清瀬一光さんは他の素材にも蒔絵を施すことに挑戦しました。
ガラスやべっ甲、象牙などです。
この挑戦が「加賀蒔絵」の技術を向上させ、更に見事な作品を作り上げる事へつながりました。
今までに無い新たな試みに挑戦したことにより「加賀蒔絵」の可能性がまた一つ広がりました。
平成7年に二代目「清瀬一光」さんは通産大臣認定伝統工芸士となり現在は「金沢漆器」「加賀蒔絵」の魅力、文化を広く世界へ広めると共に次の世代へ向けて後進の育成に尽力されているとの事です。
人間国宝(重要無形文化財保持者)の漆芸家である音丸耕堂(おとまる こうどう)は、香川県高松市に生まれます。驚くことに小学校を卒業後、13歳で讃岐彫りを専門とする石井磬堂(いしい けいどう)に弟子入りし、4年間讃岐彫りを学びます。その後、16歳で独立したのちに20歳のとき香川漆器の玉楮象谷(たまかじ しょうこく)の作風にひかれて私淑して彫漆を独学し、「堆朱」・「堆黒」・「紅花緑葉」など古来の色漆を用いた彫漆を行いました。昭和7年(1932)第13回帝展に「彫漆双蟹手箱」で初入選して以後は、官展を中心に出品し、昭和12年(1937)上京してからというもの、色漆の色彩の幅を広げ、新色を用いる試みを行いました。昭和30年(1955)重要無形文化財保持者(人間国宝)に指定されます。日本工芸会の創立にも参加し、日本伝統工芸展にも出品を続けました。色漆に金銀粉を混入して塗り、漆の固まる間に金銀が沈澱して層をつくるのをいかし、文様があらわれるように研ぎ出す技法や、彫り口の傾斜の角度により、重ねた色漆の層の断面を加減して微妙な文様をあらわす技法など、彫漆による多様な表現の可能性を引きだしました。
小島雄四郎は、国の重要無形文化財「木工芸」保持者、黒田 辰秋(くろだ たつあき)氏に師事します。黒田辰秋は、現代漆工芸の第一人者として活躍した名工になります。修業中は、師と共に飛騨高山にて皇居新宮殿の調度品を作成しました。師の黒田辰秋に感化を受けた螺鈿細工は、伝統の味わいを湛えながらも、 現代的感覚を持った小島雄四郎ならではの作域へと変貌をとげています。旺盛な制作活動を続ける小島雄四郎さんは、阪急梅田本店 美術画廊での個展を2015年までに19回も行っています。日々の暮らしの中で使える螺鈿細工の神秘的な貝の輝きを暮らしのいろどりにできるよう作品を制作されています。
赤塚自得は、東京で代々漆芸を家業とする家系に生まれました。狩野久信と寺崎広業について日本画を学び、更に洋画を白馬会洋画研究会で学びました。
蒔絵を父から学び、明治40年(1907)に東京勧業博覧会の審査官に就任して以来、多くの審査委員を務めました。
昭和2年(1927年)第8回帝展から工芸部門が新設されると、こちらにも出品を重ね、帝国美術院会員、帝展審査員にも就任しました。
昭和5年(1930)、帝国美術院会員となり、蒔絵を専門として近代漆器工芸に伝統を踏まえながらも自らの創意で自然を描き、漆芸の近代化を進め重厚な作風は現代漆工芸作品にも大きな影響を与えています。