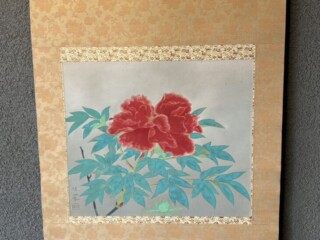森 徹山(もり てつざん 1775年~1841年)江戸時代後期の絵師です。徹山は大阪で森周峰の子として誕生。主に出身の大阪で森派、四条派として活躍しました。森周峰の実子でありますが、叔父の森狙仙の養子となり、森派を継いでいます。徹山16歳の時、「浪華郷友録」では森周峰、森狙仙の次に徹山の名前が記載されており、すでに狙仙の養子となって名の知れた絵師だったことがわかります。狙仙の勧めで晩年の円山応挙のもとで画を学ぶこととなり、のちに応挙十哲に数えられる程になりました。徹山は大阪と京都を行き来し、円山派を大阪に広めました。画風は実父の周峰から学んだ狩野派と、養父の狙仙ゆずりの動物写生に円山派の写実を加味するなど、感情豊かな画になっているのが特色です。特に動物画を得意としていた徹山ですが、狙仙とは違い猿以外にも珍しい動物なども描いております。晩年には熊本潘細川家に仕え、67歳で病没しました。
日本画家一覧
横山 華山
横山 華山(よこやま かざん 1781年または1784年~1837年)華山は江戸時代後期の絵師です。中国風に「黄華山」と署名している例もあり。出生や出身が諸説あり定かではないが、京都出身とされています。福井藩松平家の藩医の家に生まれます。幼いころは家が貧しく生計を立てるために北野天満宮で砂絵を描いてその日暮らしをしていたといいます。その後、西陣織業を営む横山家の分家にあたる横山惟馨の養子になり、本家横山家が支援していた曾我蕭白に私淑(直接教えを受けることはできないが、模範として学ぶこと)。直接誰かに師事したような形跡はなく、養父の惟馨から学んだと推測されているが定かではない。のちに岸駒に師事することとなり、大作を描き続けます。一般的に絵師は晩年になると筆力が衰えるとされているが、華山は最晩年まで大作を描き続けたという。華山の絵ではほかでは見られない特徴的な墨の使い方をしており、墨を絵具の一種として扱い、墨で書くというよりかは墨で塗るといった新しい感覚を見ることができます。日本の美術史ではあまり有名ではなかったためか、欧米の美術館やコレクターによる収蔵品が多く、ボストン美術館に13点、大英博物館に6点所蔵されている。最近になりようやく日本でも本格的な回顧展が開かれるようになりました。
熊谷 直彦
1829年1月19日~1913年3月8日 熊谷 直彦(くまがい なおひこ)は、日本画家で江戸時代末期から大正時代の京都出身の作家です。1841年に四条派の有力な画家だった岡本茂彦に入門しました。岡本の死後は独学で日本画の技術を磨いておりましたが、1844年に熊谷左門の養子となり、熊谷直彦となりました。芸州藩執政の関忠親との関わりがあり、1862年に関の側近となりました。明治維新が成就され版籍奉還が行られた後、広島藩大属となり、その後東京に出て積極的に絵画の道を再び志ます。その後、多数の作品が話題を呼びます。1884年第2回内国絵画共進会に出品した「大江山」ち「鯉」が銅賞を受け、1893年のシカゴ万博博覧会に「雨中山水」を出品。1900年のパリ万国博覧会でも同名の作品を出品しました。日本美術協会で活躍し、1903年に秋季展で特別賞状を受章するなどの功績が認められ、1904年に帝室技芸員となりました。
菊池 契月
1879年11月14日~1955年9月9日 菊池 契月(きくち けいげつ)は、長野県中野市出身の明治後期から昭和中期にかけて活躍した日本画家になります。少年の時から絵を描くことが好きで、13歳の時に南画家の児玉果亭に入門しその際に「契月」の画号を与えられます。その後画家への思いが止み難いものとなり、妹の結婚式の際同郷の友人だった、町田曲江とともに京都を出て南画家の内海吉堂に入門しますが、画風を受け入れることができずにいたことを察した内海は二人を京都の日本画家の菊池芳文に紹介。その後、菊池家の婿養子となり菊池の娘アキと結婚しました。菊池芳文の幸野楳嶺門下で、同門の竹内栖鳳、谷口公嶠、都路華薫とともに「門下の四天王」とも呼ばれておりました。1922年菊池は、画家の入江波光とヨーロッパへ視察出張に派遣され、ルネサンス期のフレスコ画や肖像画に深い感銘を受け、古典的作品の偉大さや価値を再認識し、帰国後仏教美術、大和絵、浮世絵の諸作を研究し収集しました。その成果は、1924年の「立女」や「春風払絃」となって成果が現れました。
渡辺 崋山
渡辺 崋山(わたなべ かざん 1793年10月20日~1841年11月23日)
江戸時代後期に活躍した画家。また武士でもあり、三河国田原藩の藩士でもあった。田原藩士である父、渡辺定通の長男として生まれました。しかし定通が養子であることや、定通が病気がちで医療費がかかったことにより、幼少期は貧窮の中で育ちました。画家としてみた崋山は年少の頃より生計を支えるために画業の道を志しました。出始めは大叔父にあたる平山文鏡に画の手ほどきを受け、続いて白川芝山に師事しましたが、付届け(俗にいう賄賂)ができていなかったために破門されます。父定通はこれを憐み、つてを頼り金子金陵に弟子入りを頼み、受け入れられます。金陵は崋山に目をかけたことで崋山の画力は向上しました。また金陵の師である谷文晁にも教えを受けた際に、文晁は崋山の才能を見抜きます。それもきっかけになり崋山は師文晁に倣って南画のみならず様々な系統の画派を広く吸収していきました。画家を志した理由は幼少期の貧しさ故であったが、その才が多きく花開き、また画家になる過程で出会った人脈などは崋山にとって発想をおおきくするために得がたいものになりました。
西山 翠嶂
西山 翠嶂(にしかま すいしょう)1879年4月2日~1958年3月30日は、大正から昭和にかけて活躍した日本画家になります。京都区伏見区の出身の作家で竹内栖鳳に日本画を学んだ経歴があります。1894年から各展覧会や博覧会で入賞を重ね、同門の西村五雲、橋本関雪とともに栖鳳門下として名を馳せました。努力家でもあり京都市美術工芸学校へも入学し日本画の更なる研鑽に励みました。後に翠嶂は竹内栖鳳の女婿となります。その後、文展、帝展に作品を出品し受賞を重ね1929年には抵抗美術院会員に推薦されるようになり、1937年に帝展が改組された後は帝国芸術院会員を勤めるとともに新文展審査員の職責を果たしました。竹内栖鳳の死後1944年に帝室技芸員に任命され、日本画壇の長老として重んじられました。70代になっても製作を続け、栖鳳の画風を継承した翠嶂の作域は人物、花鳥、動物、風景等に及ぶがその中でも得意としたのが、京都出身ならではの円山派や四条派を範とした人物、動物画になります。翠嶂は、後進の育成にも励み、母校の都市立絵画専門学校で教授および校長を務め、1921年頃自身の画塾「青甲社」を設立し技法を指導しました。輩出者には堂本印象、中村大三郎、上村松篁、森守明等の多くの門弟がおります。晩年には日展運営会理事、芸術院会員選考委員を務め日本美術界の発展に尽力しました。これらの功績により1957年に文化勲章を受章しました。1958年に心筋梗塞により京都市東山区の自宅で死処しました。
寺崎 広業
寺崎 広業(てらさき こうぎょう)1866年4月10日~1919年2月21日 秋田に誕生した寺崎は、幼少の頃父の職業が失敗し祖母によって育てられました。幼い頃から絵を描くことが好きで、その時から優れていたといいます。高校 …
西郷 孤月
西郷 孤月(さいごう こげつ 1873年-1912年)は明治時代に活躍した日本画家です。日本美術院の創設者のひとりでもあります。筑摩県筑摩郡松本深志町(現在の長野県松本市)に生まれる。1886年に小石川餌差町の私立知神学 …
倉島 重友
倉島重友は1944年、長野県に生まれの日本画家です。1971年、東京藝術大学大学院美術研究科を修了します。1971年、再興第56回院展で初入選したのち平山郁夫に師事します。1974年には高松塚古墳壁画模写に参加します。 …
岩沢 重夫
大分県日田市豆田町に生まれの日本画家・岩沢重夫は幼少の頃は、学校に行く前に魚釣りのに行くほど川が大好きな少年でした。晩年の水辺に緑の山や季節の花を描いた小品を制作しましたが、それは全て魚釣りをするときの視点に基づいて …
後藤 順一
後藤順一は1948年生まれで京都府出身の日本画家です。少年の頃から画家を志し、京都市立芸術大学に入学します。日本画を専攻して大学院まで進み、1973年に卒業します。その翌々年には沖縄海洋博に作品を発表し、作家デビューを …
下保 昭
下保昭は昭和から平成時代の日本画家です。下保昭は、昭和2年に富山県砺波市で誕生しており、昭和24年には西山翠嶂の師事し、さらには日展で活躍しています。また、昭和45年には日展常議員に選定されており、昭和57年には日本芸 …
清水 達三
清水達三は、人物画を得意としている日本画家で1936年に和歌山県で生まれました。美人画で有名な中村貞以に師事し絵を学び、1963年に人物画で院展入選を果たし画家として活動を始めます。 しばらく人物画を描いていましたが、風 …
松尾 敏男
松尾敏男は「花の松尾敏男」を称された花鳥画にて有名な作品が多い日本画家です。 1926年に長崎県に生まれた松尾敏男は東京府立第六中学校に在学中は体操選手であったが画家を志したことから同じく花鳥画に優れた作品を多く残した堅 …
高橋 天山
高橋天山は東京都出身の日本画家です。1979年に東京造形大学を卒業します。油彩画より日本画に転向し、院展常任理事・今野忠一に師事します。1999年には日本美術院同人に推挙されます。2008年に雅号を高橋天山としています …
奥田 元宗
奥田元宗は 1912(明治45)年、広島県双三郡八幡村(現在の三次市吉舎町)に生まれます。小学校4年生の頃から、図画教師であった山田幾郎教諭の影響で絵を描き始める。1930(昭和5)年に上京し、同郷の日本画家・児玉希望 …
後藤 純男
後藤純男は昭和5(1930)年、千葉県東葛飾郡関宿町(現野田市)で真言宗豊山派住職の子として生まれます。昭和27(1952)年の再興第37回日本美術院展覧会(院展)初入選を皮切りに、昭和61年内閣総理大臣賞、平成18年 …
平松 礼二
平松礼二は1941年に東京都中野区に生まれた日本画家です。 愛知県立旭丘高等学校美術科、愛知大学法経学部卒業。 横山操に私淑し、1960年より青龍社展に出品します。 その後、個展を開催し、様々なコンクールに出品して多数の …
田渕 俊夫
日本画家・田渕敏夫は東京都江戸川区出身です。1965年、東京藝術大学美術学部日本画科卒業します。1967年、同大学大学院日本画専攻修了。師系は平山郁夫となります。1968年、再興第53回日本美術院展覧会で初入選し、19 …
木村 圭吾
木村圭吾(きむら けいご)は、昭和十九年(1944年)に京都府京都市深草に生まれた日本画家です。中学時代から画家を志し、山村眞備に師事して日本画の基礎を学びました。その後、京都市立日吉ヶ丘高等学校日本画科を卒業し、さらに …
堀 文子
堀文子は東京都出身の日本を代表する女流画家です。画家を志して、女子美術専門学校(現・女子美術大学)に入学し、在学中から新傾向の日本画制作を実践する新美術人協会展に出品します。戦後も創造美術、新制作協会日本画部、創画会へ …
石踊 達哉
石踊達哉は1945年生まれの日本画家です。 満州で生まれ、終戦後日本に帰国して鹿児島で18歳までを過ごしました。 その後は名門・東京藝術大学へ進学し、大学院まで進みました。卒業後はシュルレアリスム色の強い人物画にこだわ …
金島 桂華
金島桂華は広島県出身の日本画家です。 14歳の時に大阪に出て、西家桂州や平井直水といった画家のもとで日本画を学びました。 19歳で京都に移り、竹内栖鳳の画塾「竹杖会」に入門します。1918年の第12回文展で初入選すると …
小村 雪岱
小村雪岱は埼玉県川越市生まれの大正から昭和初期の日本画家、版画家、挿絵画家、装幀家です。1908年、東京美術学校日本画科選科卒業します。1914年、泉鏡花『日本橋』(千章館)の装幀を手がけ、以後、鏡花本のほとんどの装幀 …
森田 沙伊
日本画家の森田沙伊は1898年に北海道で生まれました。本名は才一です。幼い頃に四条派の画家佐々木蘭斎に学ぶます。1917年に上京し、川端画学校に入学します。東京美術学校で川合玉堂、結城素明に師事します。1928年帝展初 …