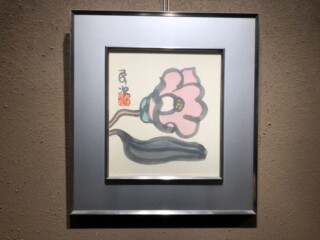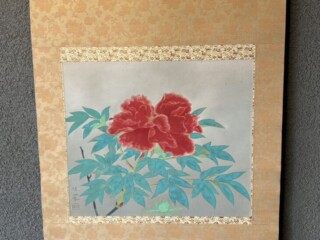西村計雄さんは1909年の北海道出身の画家です。
幼少の頃から画家になることを志し、1929年に東京藝術大学に入学をしました。同期として岡本太郎さんや東山魁夷さんがいます。
この頃は家族をモチーフにした作品を手掛けており、戦後である1949年からは早稲田中学校・高等学校の教師をしておりましたが、1951年には単身渡仏をします。パブロ・ピカソの画商であったカーンワイラー氏と出会い、1953年パリを中心としたヨーロッパ各地での個展を開催いたし、作品の多くをフランス政府が買っていきました。1971年にフランス芸術文化勲章を受勲を致しました。1973年広島県にあります「広島平和記念資料館」300号の作品を寄贈されました。その後8年の歳月をかけ、300号の大作を20点作成してきました。
1990年、1992年に「西村計雄美術館」が2店オープンします。1995年には自身の地元でもある共和町に100点を超える絵画を寄贈します。これをきっかけに1999年地元の北海道共和町に「西村計雄美術館」が作られ、後に絵画5000点や愛用していた道具など数多くのものが寄贈されています。
2000年アトリエにて逝去されました。

北川民次は日本の洋画家であり、児童美術の教育者としても活動した人物です。
北川民次は1894年、静岡県に生まれます。
地主でもある北川家は製茶業を営んでおり、アメリカへの日本茶輸出も手掛けていました。小学校卒業と共に静岡商業学校に進学します。1910年に静岡商業学校を卒業し、早稲田大学商学部予科に進学して東京都新宿区にある高田馬場というまちで下宿します。予科で上級だった洋画家の宮崎省吾(みやざきしょうご)に手ほどきを受け、1912年頃から絵を描き始めました。
1914年に早稲田大学を中退し、カリフォルニア在住の伯父を訪ねアメリカへと旅立ちます。
兄の家に身を寄せながら、レストランで働き、語学学校に通いながら英語を学びました。1年余りでアメリカの西海岸から1916年初頭にニューヨークへと渡ります。ニューヨークでは舞台の背景などを平面的に描いて設置する大道具の仕事、書き割りを生業としていました。この経験が後に構図のセンスにつながったといわれています。
1919年には美術研究所であるアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに入学します。夜間コースを開催していた講師である画家のジョン・スローンに師事します。1921年には美術研究所を卒業しました。
1922年にニューヨークからメキシコへ渡り、しばらくは聖画の行商を行いました1923年にサン・カルロス美術学校に入学し、三カ月で課程を修了し卒業、1924年にはメキシコシティー郊外のチュルブスコ僧院に附属した野外美術学校のスタッフを務めました。1925年にはメキシコシティー郊外のトランバムの野外美術学校で正規職員として教えはじめ、野外美術学校の生徒の作品展ではメキシコ大統領や文部大臣などが称賛、ヨーロッパにも巡回されてパブロ・ピカソ、アンリ・マティス、藤田嗣治などが称賛しました。
1931年には同学校の校長となりました。
この間の1929年には駐日スペイン大使の娘を看護した縁でスペインを訪れ、同大使のメキシコ転勤の際にメキシコに同行していた日本人看護師の二宮てつ乃と出会い、結婚します。1930年には長女が生まれました。
1933年には南北アメリカを旅行中の藤田嗣治とその妻マドレーヌが、一週間に渡って北川民次の家に滞在したといわれています。
計22年間滞在したアメリカとメキシコでは自由と民主主義を基本的思想とし、メキシコでは銅版画の技術を習得しました。。1936年の42歳の時に野外美術学校を閉鎖、妻子とともに日本に帰国しました。この帰国は、グッゲンハイム助成金を得ることや、長女を日本で教育させるための帰国でした。
帰国後にはまず静岡県に滞留し、その後、妻の実家がある愛知県瀬戸市で1年近く過ごしました。この時、二科展に5点を出品し、藤田嗣治の推薦で二科会会員となりました。
帰国後の数年間は油彩画やテンペラ画以外でも精力的な制作活動を行っており、水彩画や版画でも重要な作品を残しました。当時の日本の洋画壇の中では異質の画風を持ち、北川民次はメキシコ派と呼ばれました。
1944年から終戦までは愛知県立瀬戸高等女学校の図画講師を務め、終戦後は二科展のほかに、美術団体連合展、日本国際美術展、現代日本美術展、国際具象美術展、国際形象展、太陽展などに精力的に出品を行いました。
1949年の夏と1950年の夏には、名古屋市の東山動物園内に名古屋動物園美術学校を開校します。美術学校は好評でしたが、移転の話がなくなり、1951年には名古屋市東山に北川児童美術研究所を設立しました。
この頃には高知・福井・新潟・長野などで美術教育に関する講演を行っています。
1952年には創造美育協会の発起人となり、全国を回り「創造美育運動」のセミナーを開催しました。同年には中日文化賞を受賞。
このように終戦後は壁画制作の研究や美術教育の実践などに力を入れていたため、展覧会への出品数は他の期間に比べて少なかったといわれています。
1968年には瀬戸市に隣接する東春日井に転居し、1970年、前後には母子や花などのエッチングに精力を傾け、1970年の1年間には60点を超える銅版画を製作している。メキシコ時代から水墨画も描いており、1970年前後には水墨画でも多くの作品を残しました。80歳に近づいた1970年代半ばには、新しい画題として静岡県の茶畑を取り入れました。
1978年に二科会会長の東郷青児が死去すると、後任として二科会会長に就任したものの、同年9月に会長を辞任し、1979年には二科会も脱退しました。脱退と同時に画家としても活動を終えると表明したため、これ以後の作品はほとんどなく最晩年の1985年~1987年にアクリル絵の具で色紙に描いた作品が10点ほどあるのみです。
1986年にはメキシコ政府から外国人に対する最高位の勲章であるアギラ・アステカ勲章を授与されました。
1989年に死去。享年97歳でした。
石川県出身の雪深い北国の風景を描いた画家として有名なのは塗師祥一郎です。
1932年に陶芸家の塗師淡斎の長男として石川県小松市に生まれた塗師祥一郎は生まれて間もなく埼玉県の大宮に父の仕事の関係にて転居します。
しかし、戦況が悪化したことに伴い再び小松市に戻りました。
塗師祥一郎が画家を目指すきっかけとなったのが1947年に北国現代美術展に「静物」を出品して吉川賞を受賞したことがきっかけとなっております。
1950年には金沢美術短期大学に入学し、集中講義に来ていた小絲源太郎と出会い金沢美術短期大学の卒業後には大宮に転居して小絲源太郎に師事するようになります。その後は日展などに出品を重ねて数々の賞を受賞します。1967年には2か月に渡ってフランス、イタリア、スペインを周遊しそれまでは憧れをもって眺めていた西洋の風景画が日常的な風景であったことを知り、日本の風景を描くことの意義を再確認しました。その後も日展評議員や日本芸術院会員となり、2008年には旭日中綬賞を受賞し、没後には塗師祥一郎追悼展が開かれました。
マリーローランサン(1883年~1956年)はエコール・ド・パリの中でも数少ないフランスの画家です。エコール・ド・パリとは主にパリに集まった外国人芸術家集団であり、特定の流派はないが文化的・民族的背景を感じさせるものが目立ちます。
優雅な作風で「少女」を描いていることで有名なマリー ローランサンですが、絵を描き始めた当初から少女を描いていなかったそうです。
初めは、ピカソやブラックとの交流から「洗濯船(バトー・ラヴォワール)」に参加したことからその影響を受けた作風となっています。
しかし、パステル調のカラーや曲線的な形態の芸術を追求していくとキュビズムの作風と合わなくなり脱退します。
その後は独特の繊細な色彩や憂いを帯びた少女を描きエコール・ド・パリでも経済的に自立した作家となっていきました。
しかし、第一次世界大戦や結婚したことによる亡命などによって一時期、描く作品はどこか痛みを感じる作品を数は少ないですが描くようになります。
戦後にパリに戻った時には狂騒のさなかであり、マリーローランサンの描く作品は圧倒的な人気を得ることになります。
自身の名声が高まるにつれて描く作品も幸せそうに感じる作品が多くなっていきました。マリーローランサンは生涯ほとんど男性を描くことはなく、女性の美を追求した作品は日本でも人気があります。
後藤純男は昭和5(1930)年、千葉県東葛飾郡関宿町(現野田市)で真言宗豊山派住職の子として生まれます。昭和27(1952)年の再興第37回日本美術院展覧会(院展)初入選を皮切りに、昭和61年内閣総理大臣賞、平成18年旭日小綬章、平成28年に日本芸術院賞・恩賜賞など数多くの賞を受賞します。後藤純男の作品は宗教的荘厳さが漂う作品で日本画壇に比類ない存在感を放っています。郷里の慣れ親しんだ田園風景に始まり、各地を取材しながら風景を描き、厳しい自然の姿を見せる北海道の滝の連作、深い情趣を湛える季節の移ろいをとらえた法隆寺などの大和古寺のシリーズ、そして中国の雄大な山河や穏やかな農村風景など、様々なテーマに挑んだ作家です。
緑和堂では、後藤純男の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、ご気軽にお問い合わせください。
平松礼二は1941年に東京都中野区に生まれた日本画家です。
愛知県立旭丘高等学校美術科、愛知大学法経学部卒業。
横山操に私淑し、1960年より青龍社展に出品します。
その後、個展を開催し、様々なコンクールに出品して多数の賞を受賞し、その技術力を世に広めていきます。
1994年には多摩美術大学教授(2005年に退任)、2006年には了徳寺大学学長を歴任するなど、自身が研鑽を積むだけではなく、後進の育成にも力を入れています。
岩彩、箔、墨、コラージュ等、多彩な技法を駆使した21世紀を代表する日本画家のひとりです。2000年から2010年まで「文藝春秋」の表紙画を担当しています。伝統的な日本画技法に加え、ヨーロッパ印象派の光と色彩を取り入れた革新的な日本画を描きます。美しいものへの憧れが、作品となっています。
緑和堂では、平松礼二の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。