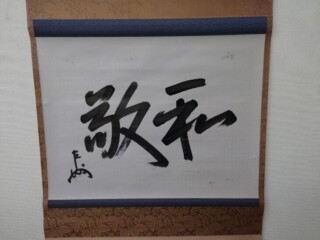中野孝一は「蒔絵」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家で、特に高蒔絵を得意とされております。
高蒔絵とは漆を何度も塗っては乾かしての作業を繰りかえすことで模様を作っていく技法で、塗り重ねる時に漆の厚さを変えたり、研ぎ具合を変えることで文様などを立体的に見せることができます。
中野孝一は変わり塗を独自に応用した蒔絵や研出し蒔絵、螺鈿や平文、卵殻などを駆使した様々な表現を得意とされており、作品のモチーフは栗鼠(リス)やうさぎなどの可憐な小動物を用いることが多く、躍動感に満ちた姿を生き生きと表して軽妙な独自の作風を表していることから高い評価を得ております。
また、中野孝一の木地作りから下地作りや蒔絵などの工程を一貫して自身で行っていることで漆芸の風合いを大事にされており、漆の持つ黒を引き立たせるために蒔絵には金粉を使うといったこだわりを持っております。
中野孝一は作品を作る上で毎日の積み重ねが重要であると考えており、基本の積み重ねで初めてその人の独創性や個性が発揮されると考え、人から見えない部分への誠実さを踏まえた上で毎日コツコツと作品を制作することで良い作品が出来上がると考えております。
増村紀一郎は2008年に「髹漆 」にて国の重要無形文化財に認定された東京都出身の漆芸家です。
「髹漆 」とは昔からある漆芸の技法であり、素地の材料を選ぶことから始まり、下地工程を経て、上塗・仕上げ工程に至る幅広い領域にわたり、漆芸の根幹をなす重要な技法であり、素地の材料には木材、竹、布、和紙、革等さまざまあり、髹漆(きゅうしつ)は素地を選ばず、各材質の特色を生かした作品作りが可能です。麻を漆で塗り何枚も重ねて風合いを出す乾漆という技法がありますが、増村紀一郎の作品はそれだけにとどまらず、中には動物の皮に漆を塗った「漆皮」という技法もあります。この漆皮という技法は平安時代以前より確立されていた技法であるといわれており、木材の加工技術の向上により廃れてしまったのではないかといわれております。
このような技法を駆使して増村紀一郎はあらゆるものを漆工芸品と変化させており、その作品は多くの人々を魅了しているに違いないでしょう。
玉川宣夫は「鍛金」にて国の重要無形文化財に認定された新潟県出身の金工師で、鎚起銅器をベースとした木目金の技法を使った作品が評価されております。
鎚起銅器とは新潟県の燕市にて作られている銅器で江戸時代中期に誕生した伝統工芸品で弥彦山から取れる銅を使ってやかんなどを制作しておりました。鎚起とは鎚で起こす打ち物のことで、銅という伸縮性を利用して一枚の銅板を打ち起こしていくには熟練の技が求められ、そうして出来た鎚起銅器は長年手入れをすることで銅の風合いが増すことや、一つの製品に数十万回と内を加えていく為、外側は陶器と思わせるように制作することが可能であることが特徴的です。
木目金とは、今から400年ほど前に生まれた金属の色の違いを利用して木目模様を作り出す技術であり、銅、銀、赤銅(銅に金が3%含有)などの色の異なる金属を20から30枚程度重ねて融着させ、金属の塊を作り、それを金づちで打ちながらまた鏨で表面をそり落とすことで木目模様にした後に、器へと成型をします。
この木目金の第一人者こそが玉川宣夫であり、海外でもこの木目金は「MOKUMEGANE」と言われて、有名です。
皆様は山岸一男という人物をご存知でしょうか。
山岸一男は2018年に「沈金」の分野にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された石川県出身の漆芸家です。沈金という輪島塗の加飾技法の会得に加え、沈金の一種で金の代わりに漆を塗る沈黒といった技法や輪島にて沈金の応用として発展をした「沈金象嵌」といった表現を用いることで作品としての可能性を広げました。
山岸一男の作品には様々な工夫が施されており、沈黒には繊細な質感表現、沈金象嵌では彫溝に自身で加工をした赤や緑といった色漆を埋めて研ぐことで様々な色彩表現を可能とし、これらの技法を組合わせながら北陸の自然や風景を大胆に映し出し、現代観溢れる作品であるとして高い評価を受けております。
1973年に第23回日本伝統工芸展に初入選したこと皮切りに数々の賞を受賞し、2004年には石川県より紀宮様へ献上した「沈金象嵌深山路小箱」を謹製したことでさらに評価を受けることとなります。そして、これまでの功績が称えられ2012年には紫綬褒章を受章、2018年には国の重要無形文化財に認定されました。
北村昭斎は「螺鈿」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家です。
螺鈿とは漆工芸品の加飾技法のひとつで貝殻の内側の真珠層と呼ばれる光沢を帯びた虹色の部分を文様にして切り出し、漆地や木地などに彫刻した面にはめ込む技法で、奈良時代に中国から伝わったものであるといわれています。「螺」は螺旋状の殻をもつ貝のことを表し、鈿は金属や貝による飾りのことを表し、生地ではなく逆に貝の裏面に直接着色をしたり、金銀箔を貼ったりしたものは色底螺鈿といいます。
螺鈿に使われる貝には厚貝と薄貝があり、厚貝は乳白色を基調とした真珠光沢のような色をしており、薄貝は膜層によって青や赤といった色の変化があることが特徴的で、歴史的には厚貝が最初で、のちに薄貝が定番となり、螺鈿が青貝ともいわれるようになってのは、薄貝にて青い色を出せるようになったからです。
北村昭斎の作品は、厚貝螺鈿技法を会得し伝統技法踏まえた上で新たな工夫を加えること、素材特有の色彩を菱文や花文と組み合わせるて効果的に配することで大胆で意匠的、現代的な美しさを持つものとして高く評価されております。
代表的な作品としては第45回日本伝統工芸展に出品し、朝日新聞社賞を受賞した華菱文玳瑁螺鈿箱があります。
京焼の伝統的な作品を製作している陶芸家として有名な久世久宝という家元をご存知でしょうか。
京焼の伝統を踏まえながらも仁清写色絵付や染付、金襴手などの技法を持つ陶芸家で、当代が5代目となります。
初代久世久宝は1874年に幕末の僧であった仁渓の子として生まれ、芸術作品に触れる事や高い精神を持つようにと鍛錬を続けている家系に生まれています。
作陶を始めてからは仁浴と名乗り大田垣連月らと親交を深めておりました。
仁浴の技術を裏千家13代圓能斎に認められてからは久宝という名を拝受しております。
久世久宝の作風としては女流作家として知られていることもあってか繊細なタッチと華やかな世界観を感じさせてくれることが特徴的であると言えます。
特に3代目製作の金襴手宝尽茶碗は美しい中にもどこか女性特有の可愛らしさを感じさせるような作品となっており、今も見るものを魅了しているのではないでしょうか。
今後も久世久宝の作品は多くの人々を魅了してくれることでしょう。